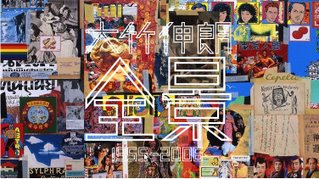本日は、エリエスブックコンサルティングが主催する
「これから10年愛される作家になるために」というセミナーを受講してきました。
エリエスブックコンサルティングといえば、
元アマゾンのカリスマバイヤー土井英司さん。
多くのビジネス書などを仕掛けてきている土井さんが
どんなことを考えているかに興味をもって参加してきました。
気になったことをメモしておきます。
ちょっとメモなので、わかりづらいところも多いと思いますが。
1.なぜ本を書くと人生が加速するのか?
自分のキャラを理解しているか?
自分が誰に好かれるのかを認識すること。
自分と同じ価値観、理念に共感する人がどのくらいいるのか?
出版することが目的ではない。
本を出すことで、その世界のオピニオンリーダーになる。
だから、本を出すと人生が加速する。セルフイメージが上がる。
人は「影響力」がほしい。
だから「人を動かす」は売れ続けている。
オピニオンリーダーは、情報や人脈を求め続けている。そこに入れるかどうか。
メッセージが重要。
別に本じゃなくても、CDでも、映像でもWEBでもいい。
Y(売り上げ)=a(コンテンツ力)x(マーケティング)+b(おまけ。販促キャンペーン)
だから、コンテンツが大事。
本を読んで、どれだけの人が動くのか?影響を持つのか?
だからaが重要。
ネットの時代にとって、「表現の技術」は重要。
ネット上では、絶対にものにふれられない。だから、表現が重要。
それによって売り上げが変わる。
逆に、人に会う、触れ合うなどの行為が非常に高級なものとなっていく。
「言葉」も「人間」もメディア。
コンテンツは自分自身。「何を言うのか?」の時代から「誰が言うのか?」の時代
結局、人の話題になるのは「人」か「物」の話。
話題の大半は「人」についてのはず。
2.作家になるために求められること
・自分を知ること
自分を外から見れること
茂木健一郎さんの言う「自己反省文」のようなトピックス
自分の人から思われていて、なかなか指摘できないようなことを自分で言ってしまう。
そうすると、周囲は言っていいということで一気に広まっていく。
みんなつがっているから、あっという間に広がっていく。
・言語化の技術
インタビューを受けるときにも、言語能力によって
露出に大きく差が出る。
小泉元総理は、トピックスを15秒に収まるように露出していた。
・ブランディング
人は変わっていっても、ブランドは固定化されやすい。
間違ったブランドを行わないこと。特に手段をブランド化すると
時代が変わったときや、手段が変わったときに影響を受けやすい。
ex.石炭王の○○、そろばんの○○、ポジティブシンキングの○○
・良いパートナー選び
出版社や編集者を選ぶときには慎重に。
編集者は最初の読者。一緒に仕事をやり通せる人だけ仕事をすること。
出版社の特徴や色に注意。自分のテーマと合っていないと本が売れない。
・マーケティング
出版流通をキチンと学ぶこと。
地味だが非常に重要。
・メディア戦略
・ふさわしい人格とセルフイメージ
信用を大切にしているか?出版は狭い世界。
・継続力(探求心、情報、人脈)
間違ったブランドを創ってしまうと、、、
常に世の中の状況をウオッチして、自分の位置づけを知っておくこと。
3.作家志望者のカン違い
創作物を書いていたとしても、自分の価値観は文章に入る。
物の見方や作り手の人間性。
江藤淳さんは「作家の作品はその時代の影響を受ける」と言っていた。
その時代や、その人の見方によって、物事を見る目は変わってくる。
いかに、人は正しく物を見ていないか。
4.売れている本はすべてフィルターで売れている
「国家の品格」はノウハウを得るために売れているわけではない。
あくまで、物の見方、藤原さんの意見に共感して売れている。
だから、自分のフィルターを明確にしておく必要がある。
どんな主張、どんな意見、どんなことで共感させられるのか?
5.自分自身のフィルターを知るためにどうするべきか
他人の視点と比較してみる。
注意しているものが違うはず。
すべての物を「好き」と「嫌い」で分けてみる
そして、その違いがどこから生まれているか一段上から考えてみる。
一流の人間に触れることで、自分のグレード、スケールがわかる。
一歩上の視点から見ると、発言の説得力が違う。
6.これからは書籍が求められる時代
netで情報がますますあふれてくる
→まとめたものがほしい
→整理して、理解するためのものがほしい
だから、「ものの見方を売る」=親書がやっていること。
今、新書が売れているのはこれが背景としてある。
7.ノンフィクション→フィクションの時代「虚にして虚あらず、実にして実あらず」
お金、ビジネスにかかわるものが売れている。
書籍=教養の時代から、実用にシフトしてきている。
今までは、「職業作家」「職業芸能人」「職業アナウンサー」の時代だった。
今後は、情報を持っている人やその分野の専門家で話がうまい人がメディアに出る時代へ。
すでに、話のうまい「弁護士」「医者」などがタレント化している。
今後、TVが他チャンネル化してくると相対的にギャラが下がり、
しゃべりのうまいプロフェッショナルが重宝がられる。
8.売れる作家になるために 出版マーケティングの視点
マーケットのグループを理解する
信念のグループ、自分の主張に共感するグループはどのぐらいいるのか?
どの表現に共感し、どの表現に共感しないのか?
たとえば、「魔法」というワードは女性にはいいが、男性にはNG
出版社によって、どのジャンルにおかれるかが決まってくる。
出版は、早ければ早いほど効果が大きい。なぜなら効果が持続するから。
ファンがつく。実績があると初版の部数が上がるから。
本田健さんは「初版を上げ続けられる著者になりたい」と語っているそう。
土井英司さんは、自分自身のフィルターが「影響力」というだけあって
人脈は「数ではなく、質」や、自分が一日動いたことによる話題にあがる
影響の循環の話など、自分のまわりで起こることをわかりやすく話していただきました。